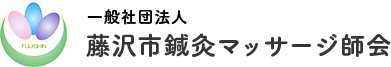1江の島に生きた鍼師 杉山和一検校日本の鍼灸手技療法の中興の祖
杉山和一検校の生涯(1610 年~1694 年)
江戸時代前期の鍼医杉山和一は、1610 年(慶長 15)伊勢国・藤堂和泉守高虎の家臣杉山権右衛門重政の長男として伊勢の津で生まれました。幼名は養慶。幼少期に病により失明し家督を継げず、鍼で身を立てようと江戸の盲人鍼医・山瀬琢一の門弟となりますが、物覚えが悪く不器用なため鍼術が上達せず破門されてしまいます。
和一は、失意のうちに訪れた江の島で、鍼が上達するよう弁財天に祈り断食修行を行います。その満願の日、精魂尽き果て倒れたところ「福石」に躓き、木の葉に包まれた松葉の先がチクリと手に触れたことをきっかけに、日本独自の刺鍼技術である「管鍼法」の発想を得たと語り継がれています。
その後、京都の入江豊明に師事し研鑽を深め、管鍼法を完成させ、江戸に戻り開業します。名声が大いに上がり施術所は門前市をなしていたそうです。
1670 年(寛文 10)60 歳で検校となり、1682 年(天和 2)に鍼術再興のため「鍼治講習所」を開設します。この鍼治講習所は、世界に先駆けて行われた視覚障がい者の職業教育機関とされています。1685 年(貞享 2)1 月 8 日綱吉に謁見、綱吉の持病を鍼治療で治し大きな信頼を得ます。1692 年(元禄 5)5 月 9 日、関東総検校に任ぜられ、1694 年(元禄 7)5 月 18 日死去。法名は前惣検校即明院殿眼叟元清権大僧都。
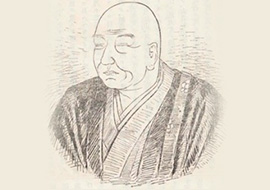
杉山和一

検校が躓いたとされる福石(臥牛石)
杉山和一検校の功績
(1)管鍼法の大成
従来の打鍼法、撚鍼法よりも扱いやすい「管鍼法」を大成し、鍼治療に革新的な成果を上げたこと。管鍼法は、操作が簡単で、鍼の無痛刺入を容易にし、経穴を正確に捉えられることなどの利点がある。日本独自の刺鍼技術で、現在日本の多くのはり師が用いている。

管鍼法
(2)世界初の視覚障がい者職業教育施設である鍼治講習所の創設
世界初の視覚障がい者職業教育施設である「鍼治講習所」を創設して視覚障がい者に組織だった教育の場を与え、芸能だけではなく鍼灸・あん摩の職業教育という新しい職の分野を開いたこと。
視覚障がい者の職業として鍼灸・あん摩を定着させることにより、自立の道を開く基礎となった。その後の障がい者教育、障がい者自立と、社会福祉に与えた影響は大きい。この後に続く視覚障がい者教育施設としては、約 100 年後の 1784 年頃にフランス人のバランタン・アユイが、パリで盲学校を開設している。
2杉山和一と江の島
杉山検校はその生涯において、月一度の江の島詣を欠かさなかったと言われるほど信仰が篤く、江の島下之坊への護摩堂・三重塔の建立や江の島道標の寄進を行うなど、江の島との関わりは深い。歌川広重の浮世絵「東海道五十三次 藤沢宿」には、検校を慕う盲人らの江の島詣の様子も描かれている。
江の島弁財天への寄進
杉山和一は、江の島弁財天への信仰心が篤く、1692 年(元禄 5)に護摩堂の建立、1693 年(元禄 6)に三重塔の建立を行っている。三重塔は明治時代の廃仏毀釈により壊されてしまい、現在は見ることはできないが、その様子は葛飾北斎作の浮世絵「富嶽三十六景 相州江ノ島」(1831-34 年頃版行)に当時の面影を見ることができる。
江の島道標の寄進
杉山検校は、藤沢宿から江の島までの 4km の間に、江の島までの道順を指し示すために置かれたという 48 基の「江の島道標」を寄進したと伝えられている。道標の形状は尖頭四角柱で火成岩製。全長は、地上部分 120~130㎝、地中部分約 70㎝、幅は 22~25㎝ 程度。道標には「一切衆生、ゑ能し満道、二世安楽」の銘が刻まれているが、これらは通常の道標よりも深く文字が掘り込まれており、目の不自由な方も触れてわかり易いようにと、杉山検校の配慮があったと言われている。

この「江の島道標」は、現在藤沢市内に 14 基確認できている(12 基が昭和 41 年 1 月 17 日、藤沢市指定文化財に指定)。またその他、鎌倉市に 1 基、世田谷区に 1 基の計 16 基が現存している。
しかし藤沢市内に現存する 14 基の江の島道標の中で、湘南モノレール「湘南江ノ島」駅付近の江の島道標の 1 基だけは形式の違うもので、杉山検校が寄進した江ノ島道標とは別のものとして考えられている。したがって、厳密には藤沢市内には 13 基(このうち藤沢市指定文化財となるのは 11 基)、鎌倉市 1 基、世田谷区 1 基の計 15 基が、杉山検校が寄進した江ノ島道標として現存しているということになる。近年、藤沢市郷土歴史課の尽力により江の島道標が整備され、いくつかの道標が江の島道の沿道に移設されている。2021 年 12 月時点の江の島道標 15 基の様子を記録(表 1)として記しておく。
表 1:現在確認できている江の島道標 15 基
藤沢市
〇1.白旗神社境内
2.遊行寺内の真徳寺境内
〇3.藤沢橋
〇4.遊行通りロータリー
〇5.法照寺境内
〇6.砥上公園
〇7.大源太公園
8.鵠沼海岸の民家
〇9.片瀬小学校南門脇
〇10.密蔵寺向い角
〇11.西行もどり松
〇12.州鼻通り
〇13.江島神社福石前(〇は藤沢市指定文化財)
13 基
鎌倉市
14.鎌倉市腰越行政センター
1 基
世田谷区
15.幽篁堂(ゆうこうどう)庭園跡地
1 基
浮世絵に見る江戸時代の江の島詣
歌川広重の「東海道五十三次 藤沢宿(保永堂版)」の浮世絵には目に障がいのある方々が、江の島詣をする様子が描かれている。遊行寺橋(大鋸橋)を渡った鳥居の下に、右手に杖を持った 4 人の目に障害のある人たちが描かれていて、この 4 人は杉山検校の故事にあやかり、これから江の島へ向かう人達です。この浮世絵以外にも「東海道五十三次 藤沢宿(隷書版)」「東海道五十三次細見図会 神奈川」「東海名所改正道中記 平塚迄三り半 藤沢 江のしまみちの鳥居」などにも江の島詣をする目に障がいのある人の姿が描かれており、この時代、江の島詣では日常の風景となっていたことが伺える。
江の島の杉山検校の墓所
1694 年(元禄 7)江戸本所の私宅にて 5 月 20 日に死去し、江戸本所の弥勒寺に葬られた(享年 85 歳)。観音信仰による遺言により命日は 5 月 18 日とされている(幕府への届出は 6 月 26 日)。永く、江ノ島の墓は分骨されたものと考えられていたが、大正 12 年 6 月 24 日の修復工事の際に、墓石の下に大甕が 1 つ埋もれていたため調査を行ったところ、首うなだれて坐っている形の、少しも崩れていない人骨が出てきたことから、江ノ島が本当の墓であることが明らかになった。笠塔婆型の墓標には以下のことが記されている。
正面:前総検校即明院殿眼叟元清権大僧都 元禄七甲戌年五月十八日
裏面 :施主 杉山安兵衛秀昌 三嶌惣検校安一 元禄八乙亥年五月十八日
側面 :追贈正五位 伊勢国津産杉山和一寂定之地 大正十三年二月十一日

杉山和一墓所(江の島西浦霊園)
(昭和 38 年 3 月 25 日藤沢市指定文化財指定)
江島神社所蔵の杉山和一木造座像について
令和元年 6 月1 6 日、江島神社内で長年行方不明だった杉山和一の木造座像が再発見されている。
木造座像の底面には、朱色の筆字にて「勢州津産 杦山氏 貞享二乙丑年五月十八日」と記されていて、1685 年 5 月 18 日に制作された杉山検校の座像であることが判明した。杉山検校が亡くなる 9 年前に作らせた自作像であり、その後の各地に存在する座像や自画像のモデルとなった可能性の高い貴重な座像である。
現在、江島神社のご厚意により修復が終了し、奉安殿に御安置され一般公開されている。